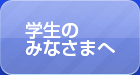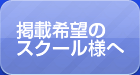内定学生引き留めに躍起 「半数以上辞退」17%
- 2014年07月31日
- 就活ニュース
企業は採用活動に時間も費用もかけています。内定辞退の伝え方によってはトラブルに発展することがあるので、選考していただいた企業に対して誠意をもって接するように心がけてほしいと思います。
2014/7/8 3:30 日経新聞 来春入社予定の新卒採用がピークを過ぎるなか、企業が学生の内定辞退防止に追われている。景気回復で今年は学生の半数が2社以上から内定を得ており、他社に目移りする学生が後を絶たない。辞退者を何とか食い止めようと、企業向けの対策セミナーも活況だ。10月の内定式まで新卒争奪戦が過熱しそうだ。
求人情報の記載内容は信じていいの?
- 2014年07月30日
- 就活と法
「求人票」の見方
インターネット上の求人情報、学校のキャリアセンターや就職課に掲示される求人票の情報を見て会社説明会に臨む就活生が多いでしょう。しかし、それらに記載されている情報は、企業が保証している「労働条件」そのものではありません。注意深く見てみると、賃金などについても「実績」・「見込み」と記載されているのが普通です。
したがって、会社説明会や面接で担当者から受けた「説明内容」が、上記のような情報源に記載さていたものと異なっていた場合には、説明会などでの「説明内容」の方が優先します。求人票に賃金見込額として記載された初任給などは、入社時までに確定されることが予定された「目標」としての額とされており、実際の額と異なるからといって、就職後に請求することはできません。
インターネットの情報だけに頼るのは危険
インターネット上の情報だけに頼って就活すると、大切な情報をキャッチできない危険性があります。会社説明会などに実際に参加し、担当者の話をしっかりと聞いて、HPなどに掲載された情報とズレはないか確認するようにしましょう。
ただし、応募者は求人票の記載内容を期待して応募している訳ですから、実際の賃金が求人票の見込額を著しく下回ることは許されないとされています(八州測量事件 東京高裁判決昭和58.12.19)。求人票に掲載された条件を「著しく下回る」ようなブラック企業であることが入社後に発覚した場合には、毅然と対応することも必要です。
東京都「就活必携労働法」を参考に作成
就活の流れを法律的に考える
- 2014年07月27日
- 就活と法
就職活動の流れを労働法の視点から見ると、どうなるのでしょうか。「内定を蹴ったら訴えられる?」「企業は内定を自由に取り消せるの?」などと、不安な気持ちで就活を始めている学生も多いと思います。
そこで今回から、就活の流れに沿って、就活生が知っておくべき労働法の知識を解説していきたいと思います。
新卒採用では、「企業の求人情報の公開」→「募集開始」→「応募」→「採用試験」→「面接」→「内定通知」および「承諾書などの提出」→「入社」という流れで就活が進んでいくのが一般的です。これを図にすると、下記のようになります。

東京都「就活必携労働法」より引用
就職活動期間は、内定・採用などの出来事によって区切られており、法律的な関係も、それぞれの期間によって変わってきます。それぞれの期間ごとにポイントを見て行きましょう。