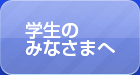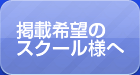大企業はいぜん狭き門 表面上の求人倍率に惑わされるな
- 2014年08月26日
- 就活ニュース
就職氷河期と呼ばれる前も大企業への就職は一部学生のための狭き門です。今も昔も大企業に入社するのはごく一部の学生であり、大半は中小企業に入社するのが現実です。
ほとんどの学生が、初めは大手企業へ入社することを夢見て就職活動を始めます。さらに、10万人超とされる就職活動経験者が就職留年生として同じ土俵で勝負することになるわけです。
身近にいる家族や社会人の先輩から、様々な意見をヒアリングすることをはじめ、将来自分が社会で働くイメージをできるだけ早くから持ってみることが大切です。就活の時期になれば毎日がとても忙しくなり、じっくりと自分の進む方向性を考える余裕がなくなるかもしれませんので、余裕があるうちに将来のことは考え始めましょう。
2014/8/17 18:00 産経ニュース
「内定をもらった企業よりもっといい企業に入りたいので就職留年する」
こんな大学生が増えています。就職留年とは大学を留年して就職活動を続けることをいいます。参考に大学を卒業して就職活動を続けることを就職浪人といいます。
毎年、多くの学生が就活留年をしていますが、今年は就職留年をする理由が今までと異なってきています。http://sankei.jp.msn.com/economy/news/
140817/biz14081718000002-n1.htm
徳島県、9月から「テレワーク」の実証実験
- 2014年08月19日
- 就活ニュース
企業には少子高齢化、地域の過疎化、労働力不足など、数々の問題があります。また、従業員にも、育児介護や長時間労働など、仕事と生活のあいだで抱えている問題が多くあります。テレワークは、そのような数々の問題を解決してくれる道具のひとつだと思います。
テレワークの導入による企業側の利点は、優秀な人材を確保できることです。経験やスキルのある社員が、育児や介護といった家庭の事情などで離職してしまうケースは多くありますが、在宅勤務などに柔軟に対応できれば、人材の流出を防ぎやすくなります。
従業員側の利点は、通勤に関する肉体的、精神的負担が少なくなることです。通勤にかかる時間を家庭に対する時間に充てることができ、仕事と家庭の両立を図ることがより可能になります。
労務管理やコミュニケーションの方法など課題はありますが、テレワークの導入によって社会の抱える問題が解決され、日本全体に大きな変化をもたらすことを望みます。
2014/8/19 3:11 日経新聞
日経新聞徳島県は情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方である「テレワーク」の実証実験を9月1日から始める。タブレット端末を活用した県庁舎外での業務など3つの実験に取り組み、ワークライフバランスの実現や業務の効率化を目指す。来年度以降の本格実施に向け、今年3月までの実証実験で課題を洗い出す。
内定取り消し=解雇
- 2014年08月05日
- 就活と法
内定の法的性質
前回の解説で述べたように、内定期間中は勤務は開始していないですが、労働契約そのものは成立しています。労働契約も「契約」である以上、内定者と企業の両方がこれを守らなければいけません。
「内定」によって労働契約が成立している場合には、企業側の都合による「内定取消し」は「解雇」と同じ意味を持ちます。したがって、労働契約法や労働基準法などで決められた、「解雇」についてのルールを守る必要があります。具体的に法律の条文を見てみましょう。
労働契約法第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。労働基準法第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。労働基準法第22条(退職時等の証明)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
内定取消には合理的な理由が必要
これらの条文に書いてある条件に加えて、企業から内定を取り消す場合には、解雇と同様、合理的な理由が必要になります。すなわち、採用内定当時に既に知っていた事情を理由とした、内定取消しは認められていません。学校を卒業できない、健康状態が悪化して仕事が出来ない、履歴書の不実記載、犯罪行為、企業の経営状態の悪化など、内定時に予測できなかった「重大な理由」がなければ内定取り消しは出来ないのです。
また、国は企業に対して、「採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること」を求めています(新規学校卒業者の採用に関する指針)。さらに、止むを得ずに新卒の採用内定取消しを行う場合には、事前にハローワークなどに通知する必要もあります(職業安定法施行規則第35条第2項)。
内定が取り消された場合には、専門家に相談することをお勧めします。
東京都「就活必携労働法」を参考に作成
内定=労働契約成立?
- 2014年08月02日
- 就活と法
「内定」って何?
就活を進めていくと、一定の時期に企業から「採用内定通知」が送られてきます。また同時に、「承諾書」や「誓約書」などの書類提出を求められます。このような手続きが始まると、企業と就活生の間には「労働契約」が成立したと考えられるのでしょうか?不安になった就活生から、毎年多くの質問が寄せられています。
裁判所の判決によると、少なくとも、内定通知と誓約書などの提出の両方が揃っていれば、「労働契約」が成立しているとされます。ただし、契約を締結したからといっても、すぐに働き始めるのではありません。通常の就活の場合、学校の卒業を条件に、4月1日から働きはじめる契約になっています。これを「始期付解約権留保付労働契約」といいます。
「内々定」とは?
一方「採用内々定」は、「採用内定通知」以前の段階で行われるもので、まだ選考の途中に過ぎません。したがって、一般的にはまだ採用が正式決定していないと考えられています。しかし、名称が「内々定」であっても、その企業の毎年の採用方法や、応募者とのやり取りの経過によっては、「契約が締結されている」と解釈できる場合もあります。不安な場合には専門家にご相談下さい。
「内定」に関する最高裁判例
「採用内定の実態は多様であるため、・・・一義的に判断することは困難であるが、本件の事実関係のもとにおいて・・・企業者からの募集に対し求職者が応募したのは労働契約の申し込みであり、これに対する採用内定通知は、右申込みに対する承諾であって、求職者の誓約書の提出とあいまって、これにより、就労の時期を大学卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解するのが相当である」
(大日本印刷事件 最高裁判決昭和 54.7.20)
東京都「就活必携労働法」を参考に作成