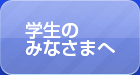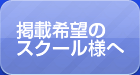就活「後ろ倒し」と学業への専念
- 2015年08月25日
- 就活ニュース
企業の選考活動の解禁が8月に「後ろ倒し」になった。学業にもっと専念できるようにという意味が込められていると8月20日の日経の「2016(有料会員限定)」で旗振り役を務めた学校法人国際大学理事長 前三井物産会長・槍田松瑩氏がインタビューに答えている。
立場により賛否両論あるところだが、とても現実的なミクロ視点での話を一つ紹介しよう。
私が以前務めていた会社での話だ。
当時務めていた会社では、新入社員が部署に配属されるのは10月。開発部署のため、工学部出身ばかりだった。
部署に配属されてからが本当の仕事で、部内のグループ(開発部品によって分けられている)にそれぞれ入れられるが、各グループ長から同じような問題が上がってきた。
私は専門ではないので、技術的なことはわからないが、基本知識が欠けているとのこと。
要するに工学部の学生を採用したのに大学で習得しているはずの知識がついてない。進められているプロジェクトに新入社員を組み込んで現場に慣れさすはずが、急遽変更となり補習授業をするはめになった。
「大学で何を学んでたんだ?」「会社は学校じゃない」などなど会議では、ため息の出る意見ばかりだった。
翌年、私はその部署ではなかったので、採用方法をどのように変えたのかは知らない。
新卒優遇思考も変なシステムだし、就活も短期戦略的で成熟した社会のシステムとは思えない。
「日本の大学は入学後は、ゆっくりしてる」と留学生や国外の大学卒業生からもよく聞く話だ。「学業がおろそか」の原因は就活システムだけではない気もするがいかがだろうか?
参考記事:日経 就活探偵団2016
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO90665810Y5A810C1000000/
試用期間の過ごし方
- 2015年08月24日
- 就活と法
試用期間とは何か
会社説明会などで、試用期間についてしっかり説明を受けておく必要があります。就活生は手取り額などの待遇面に関心が集中しがちなので、注意が必要です。
試用期間とは、被用者の勤務態度・能力・技能等を見て正式採用するかどうかを判断する期間です。試用期間中といっても、既に会社で働いている訳ですから、雇用契約は始まっています。したがって、本採用しないことは「不採用」ではなく「解雇」となるため、合理的な理由が必要となります。
この場合に要求される「合理的な理由」とは、試用期間中の勤務状態等により、採用前には知ることができなかった重大な事実が判明したような場合です。
試用期間の長さ
試用期間が長すぎたり、短い試用期間を何度も延長したりすると、労働者に対して重大な不利益を及ぼします。試用期間の長さについて、「◯年以上を禁止する」と定めた法律はありません。しかし、判例では、「労働者の能力や勤務態度等について判断するのに、通常必要な範囲を超えた試用期間については無効」としています(ブラザー工業事件 名古屋地裁判決昭 59.3.23)。
契約書によって定められた試用期間を、正当な理由なく延長することは認められません。
特殊な試用期間
契約社員など形態での契約を交わし、一定の「期間を定めた雇用」をすることで、正社員としての適性を見極めようとする企業もあります。この場合、「解雇」ではなく「契約満了」となるため、本採用しないことが簡単に可能になってしまいます。就活生にとって非常に大きな不利益になるケースなので、就活中には説明会なのでしっかりと説明を受けましょう。
なお、能力や適性について良く知っているはずのパート労働者を正社員に登用する際に試用期間を設けることはできません。