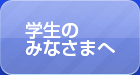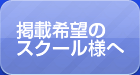こんな就活塾はヤバイ【悪徳詐欺就活塾の巧妙な手口と被害の実態 】

悪徳就活塾の巧妙な手口と被害の実態
はじめに ― なぜ優秀な学生ほど騙されるのか
「あなたは一生成功しない」
薄暗い個室で、5時間にわたる「説明会」の末、こう言い放たれる学生たち。東京都の公表資料によれば、実際にこのような言葉で追い詰められ、高額契約を結ばされた被害者が多数存在します。
2025年現在、悪徳就活塾による被害は減るどころか、むしろ巧妙化しています。特に注目すべきは、被害に遭うのは「就活に真剣に取り組もうとしている真面目な学生」だという点です。彼らは決して騙されやすい人たちではありません。むしろ、将来に対して真剣に向き合おうとしているからこそ、巧妙な罠にかかってしまうのです。
私は行政書士として、これまで多くの消費者トラブルの相談を受けてきました。その中でも就活塾被害は、若者の人生の門出を狙った、極めて悪質なものです。本稿では、実際の被害事例と最新の手口、そして法的な対抗手段について詳しく解説していきます。
第1章 デジタル時代の新たな脅威
従来型から進化した勧誘手法
2013年に東京都から行政処分を受けた「一生懸命塾」。この事件は、悪徳就活塾問題を世に知らしめる契機となりました。当時の手口は、大学周辺での声かけから始まり、事務所での長時間勧誘という、いわば「アナログ型」でした。
しかし2025年の今、彼らの手口は格段に進化しています。
■ SNS時代の巧妙な罠 – 典型的なパターン
最近の相談事例から、以下のような新たな手口が浮かび上がってきています。
【典型的なケース①:SNS経由の勧誘】
Instagram やX(旧Twitter)で「#就活 #24卒 #内定」といったハッシュタグで検索すると、きらびやかな投稿が並びます。「コンサル内定までの道のり」「総合商社に内定した私の就活術」―― 一見すると、先輩からの有益なアドバイスに見えるこれらの投稿。
このような投稿から、次のような流れで勧誘が行われることが報告されています:
- 「外資系企業内定者」を名乗るアカウントからDMが届く
- 「就活で悩んでいるようですね。よかったら相談に乗りますよ」という親切そうなメッセージ
- オンラインでの無料相談を経て、高額な就活プログラムへの勧誘
消費者庁の注意喚起によれば、これらの「内定者」アカウントの多くは、実在しない人物である可能性が高いとされています。プロフィール写真が海外のストックフォトサイトから転用されていたり、投稿内容が他のサイトからの盗用であったりするケースが確認されています。
■ オンライン面談の心理的トリック
コロナ禍を経て、Zoomなどのオンライン面談は日常的なものになりました。悪徳業者もこの変化を見逃しませんでした。
【よくある手口のパターン】
対面での勧誘と違い、オンライン面談には独特の心理的効果があります。以下のような手法が使われていると考えられます:
- 安心感の演出:自宅という安心できる空間にいる学生に対し、最初は親身な相談相手を装う
- 画面共有の悪用:派手な成功事例のスライドを次々と見せ、視覚的に圧倒する
- 時間感覚の麻痺:「あと少しだけ」と言いながら、気づけば3時間以上経過
- 決済の簡易化:画面共有のまま、クレジットカード情報入力画面へ誘導
国民生活センターへの相談事例では、「気がつけば画面共有でクレジットカード情報を入力していた」という報告が増加しているとのことです。
第2章 執拗な勧誘の実態 ― 5時間の心理戦
典型的な勧誘パターンの詳細分析
ここで、東京都が公表した実際の被害事例と、最近の相談傾向を踏まえた典型的な勧誘パターンを、時系列で詳しく見ていきましょう。
【典型的なケース②:長時間勧誘の流れ】
以下は、複数の被害相談を基に構成した、典型的な勧誘の流れです:
第1段階:接触(0分~30分)
- 大学の就職イベント会場外で「就活生の意識調査」と声をかける
- アンケート記入で個人情報を入手
- 「無料セミナーがある」と誘導
第2段階:不安の醸成(30分~90分)
- 他の学生と一緒に「就活の厳しさ」についての講義
- 「大手企業の内定率は0.1%」などのデータで不安を煽る
- 「このままでは内定は取れない」というメッセージの刷り込み
第3段階:個別攻撃(90分~180分)
- 個別ブースへの誘導
- ESや自己PRの否定
- 「君のレベルでは無理」という人格否定
第4段階:救済の提示(180分~240分)
- 「でも、うちの塾なら大丈夫」という解決策の提示
- 成功事例の紹介(真偽不明)
- 初めて高額な料金を提示
第5段階:締め付け(240分~300分)
- 断ろうとすると態度が豹変
- 「今決められない人は就活でも失敗する」
- 「親に相談するのは自立していない証拠」
- 疲労困憊になるまで勧誘継続
実際の被害事例(東京都公表資料より)
東京都が公表した実際の被害事例を見てみましょう。これらは平成24年(2012年)の事例ですが、現在でも同様の手口が使われています。
【実例1】平成24年4月の事例より
大学生の甲さんは、就活セミナー付近で「就活生の意識調査」と声をかけられ、翌日の「就活セミナー」に誘われました。
実際の被害者の証言:
「午前10時に訪問し、午後5時過ぎまで拘束されました。『金銭的に厳しい』と断ると、『日雇いのアルバイトをすればできる』と言われ、断れない状況に追い込まれました」
【実例2】平成24年8月の事例より
大学生の乙さんは、「一度帰って考えさせてください」と断った際の担当者の反応について、次のように証言しています:
「今までの親しげな様子が変わり、『そんな優柔不断な態度で、今ここで決められないようなら、今後差し迫った状況になっても決断なんてできない』と言われました」
使われる心理操作のテクニック
これらの事例から、悪徳就活塾が使用する心理操作のテクニックが明確に見えてきます。
■ 段階的要請法(フット・イン・ザ・ドア)
最初は「アンケート」という小さな要求から始まり、徐々に要求を大きくしていく手法です。心理学的に、人間は一度要求を受け入れると、次の要求も受け入れやすくなることが知られています。
■ 恐怖アピールと救済の提示
まず徹底的に不安を煽り、その後で解決策を提示する。これは「問題-解決型」の説得技法として知られ、相手の判断力を低下させる効果があります。
■ 時間的プレッシャー
「今日中に決めないと」という切迫感を演出し、冷静な判断をさせません。
■ 社会的証明の悪用
「みんな親には内緒で契約している」など、架空の「みんな」を使って、それが普通であるかのように思わせます。
第3章 法的観点から見た問題点
違反している法令の詳細
悪徳就活塾の勧誘行為は、複数の法令に違反しています。条文を挙げながら、その法的問題点を詳しく解説します。
■ 東京都消費生活条例違反
東京都消費生活条例第25条は、不適正な取引行為を禁止しています。
実際に東京都が「一生懸命塾」に対して認定した違反行為:
- 販売目的不明示(第25条1項3号)
- 「就活生の意識調査」と偽って接触
- 真の目的(高額な受講契約の勧誘)を隠蔽
- 威迫困惑・迷惑勧誘(第25条1項4号)
- 「あなたは一生成功しない」等の脅し
- 長時間の拘束による困惑
■ 特定商取引法違反
2020年3月31日、東京都は「一生懸命塾」に対し、特定商取引法違反で以下の処分を行いました:
- 3ヶ月の業務停止命令
- 代表取締役米盛みゆき氏への業務禁止命令
違反が認定された行為:
- 勧誘目的を告げずに電話で呼び出し
- 契約しない意思を示した消費者への執拗な勧誘継続
■ 消費者契約法による取消し
消費者契約法では、以下の場合に契約を取り消すことができます:
第4条3項2号(退去妨害) 実際の事例:「帰りたい」という意思を示したのに、5時間以上勧誘を続けた
第4条1項2号(断定的判断の提供) 実際の事例:「絶対に内定が取れる」「100%成功する」という勧誘
クーリングオフが使えない理由と対策
重要な注意点: 就活塾の契約は、原則としてクーリングオフの対象外です。これは、法定の「特定継続的役務提供」に該当しないためです。
しかし、以下の対策があります:
- 消費者契約法による取消し
- 不当な勧誘があった場合は取消し可能
- 取消し可能期間:追認できる時から1年間
- 民法による取消し
- 詐欺・強迫による取消し
- 錯誤による取消し
- 業者独自のクーリングオフ制度
- 良心的な業者は自主的に設定
- 契約前に必ず確認
第4章 巧妙化する手口への対抗策
2025年最新版・悪徳就活塾チェックリスト
以下のチェックリストは、消費生活センターへの相談事例と東京都の処分事例を基に作成しました。一つでも該当する項目があれば要注意です。
□ 初期接触に関する危険信号
- 大学構内や就活イベント会場周辺で声をかけてくる
- SNSで突然DMを送ってくる
- 「アンケート」「意識調査」と称して個人情報を聞き出す
- 無料セミナーや説明会への参加を執拗に勧める
□ 勧誘場所・時間の問題
- 個室や密室での勧誘を行う
- 3時間以上の長時間勧誘
- 夜遅くまで拘束する
- オンライン面談で画面共有を強要する
□ 料金・契約に関する不審点
- 料金を最後まで明示しない
- 「今日契約すれば割引」などと即決を迫る
- 総額が30万円を超える高額設定
- 分割払いやローンを強く勧める
- 契約書の控えを渡さない
□ 説明内容の問題
- 「絶対」「100%」「必ず」などの断定的表現を使う
- 具体的なカリキュラム内容を説明しない
- 成功事例ばかりで失敗例を話さない
- 他の就活支援サービスを極端に否定する
□ 心理的圧迫
- 現在の能力や経歴を否定する
- 「このままでは就職できない」と不安を煽る
- 断ると態度が豹変する
- 人格否定や将来への脅しをする
□ 相談の妨害
- 親や友人への相談を妨げる
- 「みんな内緒で契約している」と言う
- 「自立していない」などと相談を恥ずかしく思わせる
- その場での決断を強要する
被害に遭わないための具体的行動指針
■ 事前準備の重要性
就活塾を検討する際は、必ず以下の準備をしてください。
- 情報収集を徹底する
- 消費者庁、国民生活センターのウェブサイトで事業者名を検索
- 「塾名 被害」「塾名 トラブル」で検索
- 大学のキャリアセンターに評判を確認
- 録音アプリを準備する
- スマートフォンの録音機能を確認
- 長時間録音対応アプリをインストール
- 録音は自己防衛の重要な手段(相手の許可は不要)
- 同伴者を連れて行く
- 友人や家族と一緒に説明を聞く
- 「一人だけ」と言われても断固拒否
- 複数の目があれば冷静な判断が可能
■ 現場での対処法
【想定シーン別対処法】
場面1:路上で声をかけられた時
対応例:「すみません、急いでいるので」と言って立ち止まらない
重要:個人情報は絶対に教えない
場面2:しつこく勧誘された時
対応例:「条例違反ですよ」「消費生活センターに相談します」
最終手段:110番通報も検討
場面3:契約を迫られた時
対応例:「今日は説明を聞きに来ただけです」
「必ず親に相談してから決めます」
ポイント:「我が家のルール」として断固拒否
場面4:帰らせてもらえない時
対応例:「体調が悪いので帰ります」と立ち上がる
緊急時:「監禁罪で警察を呼びます」→実際に110番
録音の重要性と法的効力
録音に関する法的整理:
自分が当事者となる会話の録音(秘密録音)は、相手の許可なく行うことができます。これは最高裁判例でも認められています。
録音が証拠となる場面:
- 消費生活センターへの相談
- 弁護士への相談
- 民事訴訟での立証
- 刑事告訴(脅迫罪、監禁罪等)
推奨する録音アプリ:
- iPhoneの場合:標準のボイスメモ
- Androidの場合:Googleレコーダーアプリ
- 共通:Evernote等のメモアプリの録音機能
第5章 被害に遭ってしまったら
72時間以内にすべきこと
契約してしまっても諦める必要はありません。迅速な行動が被害を最小限に抑えます。
■ 24時間以内の対応
- 支払いの停止
- クレジットカード会社へ即連絡
- 銀行振込の場合は組戻し手続き
- 現金支払いでも領収書は必ず保管
- 証拠の保全
- すべての書類を保管
- メール、LINE等のスクリーンショット
- 勧誘の詳細をメモ(日時、場所、担当者名、発言内容)
■ 48時間以内の対応
- 消費者ホットライン188への相談
- 局番なしの188で最寄りの消費生活センターへ
- 専門相談員が対応策をアドバイス
- 相談は無料
- 大学への報告
- キャリアセンターや学生相談室へ
- 同じ被害者がいる可能性
- 大学からの支援も期待できる
■ 72時間以内の対応
- 内容証明郵便での通知
- 契約取消しの意思表示
- 行政書士・弁護士への相談も検討
- 配達証明付きで送付
- 警察への相談
- 脅迫や監禁があった場合
- 相談だけでも記録に残る
- #9110(警察相談専用電話)も活用
解決に向けた具体的アプローチ
【パターン別対処法】
ケース1:録音がある場合
想定される展開:
- 録音を基に消費生活センターが業者へ連絡
- 「退去妨害」「威迫困惑」が認定されやすい
- 全額返金の可能性が高い
ケース2:複数の被害者がいる場合
想定される展開:
- 被害者同士で情報共有
- 集団で弁護士に相談
- 業者も無視できず、返金交渉が有利に
ケース3:証拠が少ない場合
想定される展開:
- 記憶が新しいうちに詳細な陳述書作成
- 同時期の被害者を探す
- 消費生活センターの斡旋を活用
保護者の方へのメッセージ
お子様から就活塾の被害を打ち明けられた際、まず大切なのは責めないことです。
東京都の事例でも明らかなように、悪徳業者は「親に相談するのは自立していない」と巧妙に洗脳します。相談してくれたこと自体を評価し、一緒に解決策を考えてください。
予防のための家族ルール(提案):
- 10万円以上の契約は必ず家族で相談
- 就活の大きな決定は一晩考える
- 困ったらすぐに連絡できる関係維持
第6章 正しい就活支援の選び方
優良な就活支援サービスの特徴
すべての就活塾が悪徳ではありません。以下の特徴を持つサービスは信頼性が高いと考えられます。
■ 透明性の高い運営
優良サービスの公開情報:
- 料金体系(総額、内訳、返金規定)
- カリキュラムの詳細
- 講師のプロフィール
- 過去の実績(具体的な内定先等)
- 会社情報(設立年、所在地、代表者)
■ 健全な勧誘姿勢
- 説明会は1〜2時間で終了
- 検討期間を設ける
- 親御さんの同席を歓迎
- 他社との比較を推奨
- 独自のクーリングオフ制度
■ 適正な価格設定の目安
一般的な相場(あくまで参考):
- グループ講座:5〜20万円
- 個別指導込み:10〜30万円
- 全額返金保証付き:20〜40万円
※50万円超は要注意
公的機関の積極的活用
■ 大学のキャリアセンター(無料)
提供サービス:
- ES添削、面接練習
- 企業説明会の開催
- OB/OG訪問の仲介
- インターンシップ紹介
- 個別キャリア相談
■ 新卒応援ハローワーク(無料)
全国56か所に設置:
- 専門ナビゲーターによる個別支援
- 就活セミナー
- 企業情報提供
- 就職面接会
■ 地方自治体の支援(無料)
- 東京都:東京しごとセンター
- 大阪府:OSAKAしごとフィールド
- 各都道府県:ジョブカフェ
終章 就活生とその家族へ伝えたいこと
就活の不安につけ込む者たちへの怒り
私がこの問題に強い憤りを感じるのは、悪徳業者が狙うのが、真剣に将来を考えている若者たちだからです。
東京都が公表した被害事例を見ても、被害者は皆、真面目に就職活動に取り組もうとしていた学生たちでした。その純粋な気持ちにつけ込み、「あなたは一生成功しない」などと人格を否定し、法外な金銭を騙し取る。これは許しがたい行為です。
本当の「就活力」とは何か
高額な塾に通わなくても、以下の方法で十分に力をつけることができます:
無料でできる就活準備:
- 大学のキャリアセンター活用
- OB/OG訪問
- インターンシップ参加
- 友人同士でのES添削、模擬面接
- 公的機関のセミナー参加
これらはすべて、無料または低コストで実践できます。
失敗を恐れないで
就職活動での不採用は、「あなたに価値がない」ということではありません。単に「その企業との相性が合わなかった」だけです。
就活の「失敗」は人生の失敗ではありません。自分と向き合い、成長するチャンスです。
社会全体で若者を守るために
この問題は個人の注意だけでは解決しません。
- 大学関係者:キャンパス内の不審な勧誘への対応強化
- 企業採用担当者:新卒者の可能性を信じる採用姿勢
- メディア:継続的な問題提起と啓発
- 立法・行政:より実効性のある規制の検討
緊急連絡先
- 消費者ホットライン:188(局番なし)
- 法テラス:0570-078374
- 警察相談専用電話:#9110
参考資料
- 東京都生活文化局「悪質事業者処分情報」(実際の処分事例)
- 国民生活センター「就活商法に関する注意喚起」
- 消費者庁「若者の消費者トラブル」
本記事の内容は2025年11月時点の情報に基づいています。事例の一部は説明のための典型例として構成したものです。実際の被害事例については、東京都や国民生活センターの公式発表をご参照ください。
Author Profile

-
特定行政書士
早稲田大学政治経済学部卒。立教大学大学院法務研究科修了、法務博士(専門職)。帝京大学や神田外語大学他首都圏の大学で企業研究・就職活動講義へ出講経験あり。就活塾の講師としても活躍。ブラック企業や就活塾に詳しい行政書士として朝日新聞・読売新聞の取材やNHK番組出演などの実績もあり。
Latest entries
 就活と法2025年11月11日内定もらうと労働契約スタート?就活生が知っておくべき基本知識を解説します
就活と法2025年11月11日内定もらうと労働契約スタート?就活生が知っておくべき基本知識を解説します 就活と法2025年11月10日こんな就活塾はヤバイ【悪徳詐欺就活塾の巧妙な手口と被害の実態 】
就活と法2025年11月10日こんな就活塾はヤバイ【悪徳詐欺就活塾の巧妙な手口と被害の実態 】 就活と法2015年10月24日入社するには身元保証が必要?
就活と法2015年10月24日入社するには身元保証が必要? 就活と法2015年8月24日試用期間の過ごし方
就活と法2015年8月24日試用期間の過ごし方