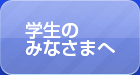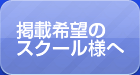“我究”なくして、ワーク・ライフバランスなし
- 2014年03月11日
- ワークライフバランス
東洋経済ONLINEに「若者にワークライフバランスなんていらない」という、ちょっと刺激的な見出しの付いた記事(2013年2月6日付)を見つけました。
ワーク・ライフバランスについては、懐疑的な意見もあるので驚きはしませんが「いったい何でまた、そんなことおっしゃいますのんや?」という興味で読んでみたところ、そこにはワーク・ライフバランスを切り口に、別次元の実にまともな議論が展開されていたので、ひとまずホッとしました。
詳細については、記事をご参照いただきたいのですが、要は、向上心とがむしゃらさがなければ仕事なんてできませんよ、という至極当然な内容でした。所々に若干、ワーク・ライフバランスの考え方とは必ずしもそぐわない記述もありましたが、趣旨については「ごもっとも!」ですよね。
訪問先のとある企業さんで「従業員から『ワーク・ライフバランス企業なんだから』と権利を主張される場面が多く、実は困っています」と担当者さんから聞かされたことがあります。この点については、就職活動真っ最中の学生さんたちにもぜひ、注意していただきたいのですが、ワーク・ライフバランスは、福利厚生的な側面だけでなく経営戦略的側面も非常に強い考え方です。仕事を充実させるための福利厚生であり、福利厚生がしっかりしているからこそ、仕事に取り組むことができる。ワークとライフはまさに、車の両輪なのです。
恐らく、仕事を生活の糧を得る場としてのみ捉えてしまうがため、生じる齟齬なのでしょう。そのような状況に陥らないためにも、仕事を単に生活の糧を得るだけの場としないよう、就職活動中から、仕事上の目標などを見定めたキャリアプランや「自分はどんな生き方をしたいのか」など、自分自身との対話をしっかりと持つことが重要です。
就職活動を支援する「就活塾」の中にも、企業から内定を得る目的にとどまらず、自分自身の仕事に対する考え方や、人生における目的を明確化するために一役買ってくれる塾もあります。直接取材させていただいたことのある「我究館」は、その名が表す取り組みを体系的に実施している機関だと感じました。
就活生のみなさんには、就活塾だけにとどまらず、多くの人や企業、本などさまざまな出逢いを通して自分を探求し“哲学”してほしいと思います。
参考記事
http://toyokeizai.net/articles/-/12808
就活中に妊娠!? そのとき会社は…
- 2014年03月01日
- ワークライフバランス
2月28日付「朝日新聞」は、衛生用品メーカーのユニ・チャームは、妊娠中の女子学生が内定した場合、入社の時期を30歳まで延期することができる制度を2015年度の新卒採用から導入する、と報じました。
記事によると、就活中に妊娠が分かり、内定を辞退した事例がこれまでに数例あったと言います。同制度の活用が今後、活発になるか否かはさて置き、世間には、優秀な女性は「少し待ってでも確実に採用したい」という企業側からの強烈なメッセージが伝わったことでしょう。
ところで、林真理子さんの「野心のすすめ」(講談社現代新書)が 45万部のベストセラーになっています。 SNSサイト「フェイスブック」coo(最高執行責任者)のシェリル・サンドバーグさんの著書「 LEAN IN 」しかり、近頃は「女性よ大志を抱け!」と士気を鼓舞する書籍が次々と話題になります。これは、少子高齢社会の進展や経済が足踏み状況の日本のあらゆる場面で、女性の力が必要とされていることが影響している結果だと考えられます。
ところが女性側からすれば、現状は、育児などの悩みから、大志を抱こうにも壁にぶつかること多々。例えば、私自身も3人の子を持つ母ですが、私が暮らす沖縄では、保育所や学童の問題1つを取ってみても、女性の社会参画に向けた環境整備はまだまだ不十分です。東京は沖縄以上に待機児童の問題は深刻ですし、全国を見渡してみれば子育て環境におけるインフラ整備の問題は、あちらこちらに転がっています。
とは言え、女性活用は社会における喫緊の課題です。入社前か、後かの順序はあるにせよ、女性のキャリア形成において、相変わらず妊娠・出産が“岐路”になってしまう現状について、先に挙げたユニ・チャームのごとく、まずは企業努力で何とか社会に変革をもたらすような果敢な取り組みが、次々と打ち出されるよう期待したいところ、です。
その為にも、就活生のみなさんの率直な意思表明は、とても重要だと私は常々考えています。
前回のコラムでも、似たようなことを書いたところ、バブル期を経験されている方から「いまの若手は厳しい環境にさらされすぎている」とのご意見をいただきました。まったく同感です。一方で、こういう厳しい状況下にあるからこその“イノベーション”にもまた、期待したいところ、なのですが…。
参考記事 http://asahi.gakujo.ne.jp/common_sense/morning_paper/detail/id=603