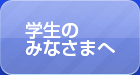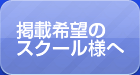新聞はキャリアアップに必要不可欠?!
- 2018年07月19日
- 将来をデザインする
最近、「新聞離れ、無料電子版」などが増加し、昔よく電車の中で見かけた新聞を大きく広げる働くお父さんもだいぶ減ったように感じます。
通勤時のニュースチェックは、「スマートフォンやタブレットで」が主流になってきているのかもしれません。
しかし、新聞にはビジネスマンにとって必要不可欠な沢山の情報が載っています。
読んだ方がいいと分かっていても、あの膨大な情報をどう読み進めていいのか分からない等を理由になかなか手を付けられていない方も多いのではないでしょうか。
今回は、読み方のポイントや新聞各社の特色など、基礎知識を中心に紹介します。
なぜ新聞を読むといいと言われているのか
新聞は、上司や商談相手とのコミュニケーションツールになります。
その話題に対してどういった意見や考え方を持っているのか、その情報から何を読み取っているのか等観察し、評価している人もいると聞きます。
共通の話題を持つことで、アイスブレイクのバリエーションも増え、ちょっとした雑談から緊張感をなくしてスムーズに商談へと移行できれば、仕事が進めやすくなるのではないでしょうか。
読み慣れるまでは、一面に出ている記事を読むことしかできないかもしれませんが、少しずつ読む記事も変化し、読解力も上がっていき、コミュニケーション能力がアップ・キャリアアップになることでしょう。
ネットニュースは、偏りが生まれる?
誰でも手軽に読める無料のネットニュース。
常に最新情報がアップされ、コミュニケーションツールとして活用すること自体はよいと思います。
しかし、自分でクリックして記事を読むので、知らず知らずの内に自分が気になるニュースや、関心のあるジャンルだけを選択してしまい、必然的に情報に偏りが生じます。
その点、新聞は政治、経済、スポーツ、社会面などさまざまな情報が載っており、それが自然と目に入ってくるので、自分の守備範囲外のことも簡単に吸収できます。
新聞は、記者やジャーナリストが本当に伝えたいこと、誠意を込めて書いた記事が載っています。
何ヶ月も準備と取材をして書いた記事、読者に分かりやすいか、内容が充実しているか、記事がおかしくないか、事実かどうか等を精査されたものが新聞となっているので当然質が高いです。
新聞各社の特色
まずこのグラフをご覧ください。


参照元:http://www.garbagenews.net/archives/2238684.html
図を見て分かるように、新聞を購読している人は70%を超えています。
しかしそのうち、2紙以上新聞を取っている人は5%に満たないです。
この結果から、何かしらを理由にして新聞1紙しか読んでいない方が多いと分かります。
1紙しか読まない理由として、各家庭の経済的な面はあるかもしれませんが、やはり新聞各社の特徴が好みに合っているかではないでしょうか?
簡単に各紙の特徴を紹介します。
日経新聞…ビジネスマン、就活生は読むべき!政治思想色は薄く中立性の高い記事が特徴。
読売新聞…発行部数1位、分かりやすさ重視。事件の報道が多い。大衆紙と言われている。
朝日新聞…発行部数2位、クォリティの高さを評価されている。政治分野多め。
産経新聞…ナンバーワンよりオンリーワン。群れない、逃げない、モノを言う新聞という独自路線。
毎日新聞…中道的な論調が特徴。若年層よりも団塊以上の世代の視点寄り。
同じニュースでも、新聞によって扱い方や視点が変化します。
各紙どのような記事で、自分の好みな新聞を探すために、一度無料購読や電子版を試すのもアリかもしれません。
新聞の効率のよい読み方、ポイント
膨大な情報量の新聞を読み進めるには、いくつかポイントがあります。
ポイントさえおさえることが出来れば、敬遠していた新聞を読むことができます。
1、1面をさらう
新聞の1面には、世間の関心が高いニュースが載っています。
つまり、世の中の動きが最もわかるのが1面なのです。
1面だけは毎日読むようにしましょう。
2、「見出しだけで済ませる記事」、「リード文まで読む記事」、「最後の本文まで読む記事」
この3段階に分けて読むと全体を読むことが出来ます。
本文まで読む記事には、赤ペンなどで二重丸、リード文までなら一重丸など付けてくと時間がない朝、あとで効率的にじっくり読み直すこともできます。
3、総合、企業の見出し
自分の仕事に最低限必要なトピックを選んで毎日読むようにすると、仕事に役立つでしょう。
4、株価
日経平均株価と円・ドルだけでも毎日チェックすれば、経済の大きな流れが見えてきます。
その他
就活などで活用するため内容を掘り下げる場合には、以下のことをすると効果的です。
・スクラップをしてまとめる作る
・コラム、社説を書き写す
・気になった記事を読了後、自分の意見や考え方、共感するのか等を簡単にまとめるようにする
まとめ
新聞は、社会人にとって、とても重要なビジネスツールです。
就活の段階から読み慣れておくことで、社会に出た時に大いに役立ちます。
自分の意見や考えを普段からまとめておくことで、咄嗟に質問された場合などにも柔軟に対応できることでしょう。
また、自分自身の意見を持つこと、軸をブレずに持っていると、そういった点を評価してくれる上司や、企業にも出会えるはずです。
最終的には、キャリアアップにも繋がると思うのでこの機会に新聞に挑戦してみてください。
質問力を鍛える
- 2018年07月05日
- 将来をデザインする
あなたの質問力、大丈夫?
あなたはコミュニケーション能力に自信がありますか?
このコラムでは、キャリアアップに必要なスキル、知識や情報をさまざまな角度からお伝えします。
今回は、コミュニケーションに必要不可欠な「質問力」にクローズアップをして、
質問力を鍛えることの重要性やメリットについて紹介です。
どうのようにしたら質問力を鍛えることができるのか・・・
そのためにやるべき5つの具体的方法をレクチャーします!
このコラムを読むことで、読者の皆様のモチベーションがアップし、キャリアデザインへの考え方や方向性を見出してもらえると幸いです。
質問力とは?
質問力とは、「分からないことや疑問に思ったことを聞く力のことです。
ただ単に気になったことを聞くことももちろん質問ですが、それではビジネスの場では活かすことが出来ません。
会議や商談、普段の業務での上司や同僚との会話でも、質問力は必須です。
今後キャリアデザインをしていく上で、必要不可欠なスキルと言ってもよいでしょう。
「自分の聞きたいことを聞く、相手が聞いて欲しいと思っていることを聞く」
このことができるようになると、コミュニケーション能力が格段にアップし、
仕事の質も周りからの評価も上がると思います。
質の良い質問?悪い質問?
質問には、「質の良いもの」と、「質の悪いもの」があります。
自分自身では、うまい(質の良い)質問をしたと思っていても客観的に判断すると、
もしかしたら違う場合もあるかもしれません。
普段の自分を振り返りつつ、読んでみてください。
質の良い質問は、具体的な質問と本質的な質問、このふたつをしています。
具体的な質問は、明確な数字を入れること、期間などを絞って質問することで相手が格段に答えやすくなります。
例
1番人気な○○、20代の頃の○○、3つの中から選んで欲しい・・・など
また、本質的な質問とは、相手の立場に立って質問することをいいます。
例
それをする目的はなんですか?
どうしてそう思うのですか?
このような質問をすることにより、相手に興味があることが伝わります。
一方、悪い質問とは、「最近はどうですか?」のような抽象的な質問です。
一見、相手とコミュニケーションをとろうとしているような質問ですが、
相手からすると答えにくい質問でもあります。
表面上のやりとりだけで、自分が得たい情報までに遠回りしてしまう場合もあります。
質問の種類
1、質問
「今できることは何?
(効果:きっかけを与える)
相手の反応→気付きを含んだ答え
2、挨拶質問
「最近の調子はどう?
(効果:コミュニケーション)
相手の反応→質問に対する返事
3、疑問
「この方法で大丈夫?
(効果:知りたいことを聞く)
相手の反応→回答を述べる
4、クイズ
「これは何ですか?」(効果:知識を試す)
相手の反応→正解・誤答
5、命令質問
「〆切りまでにできますか?」(効果:強制)
相手の反応→服従・反発
6、尋問・詰問
「どうしてミスをしたのか?」(効果:追及する)
相手の反応→言い訳
質問力を鍛えることの重要性&メリット
・問題や疑問を解決、解消できる
・相手と考え方や方法などをすり合わせることができ、相互理解ができる
・コミュニケーション能力がアップする
質問力を鍛える5つの方法
1、 質問することを恥ずかしがらず、すぐ聞くことが大切
理解していないのに分かったふりをしていることは、恥ずかしいことです。
分からないことをそのままにすると、今後の業務に支障が出てくる場合もあります。
もし、質問することを恥ずかしいと感じている方は今すぐに考えを改めましょう。
2、 質問する癖をつける
質問を作れない人は、他の人の話に興味がなく、聞いていない場合が多いです。
家族や友人達との会話で、質問する癖をつけるように意識するといいかもしれません。
疑問点を見つけて、会話を掘り下げ質問する練習しましょう。
3、 相手が答えやすい質問作りを心がける
質問する際は、大雑把な質問ではなく相手が答えやすいような質問をします。
「これについてどう思いますか?」ではなく、
「私はこう考えるのですが、あなたはどう思いますか?」など、
配慮すると相手も答えやすくなります。
4、 疑問点を書き出してみる
普段生活しているうえで、疑問に思うことがあると思います。
それを書き出してみましょう。
テレビやラジオは、質問力を鍛えるためにぴったりの道具です。
活用しましょう!
5、 周りにアドバイスを求めてみる
アドバイスを聞く癖をつけることで問題解決のスピードが早くなり、仕事の効率化につながります。
また、他の人のアドバイスを受け入れることで、新しいアイディアも生まれやすくなります。
まとめ
質問力を鍛え、高めることができれば、コミュニケーション能力も自然と身に付き、
仕事の質を向上させることに繋がります。
商談などのシチュエーションで普段聞けないような話を、相手から聞き出すことができるように
なれるかもしれません。
そのようなスキルがあれば、どんな環境下にいてもあなたは重宝される存在になるでしょう。
自分が聞きたいこと、相手が聞いて欲しいことに気が付ける質問力、この機会に磨いてみてください。