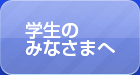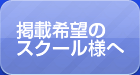内定もらうと労働契約スタート?就活生が知っておくべき基本知識を解説します

はじめに―なぜ内定と労働契約の関係を理解すべきか
就職活動を頑張って、ようやく企業から「内定通知」を受け取ったあなた。「これで就職が決まった!」と安心していませんか?しかし、内定から入社までの期間には、実は様々な法的な問題が潜んでいます。
例えば、こんな不安を感じたことはありませんか?
- 「内定をもらったけど、本当に4月から働けるの?」
- 「内定取消って実際にあるの?どんな場合に起こるの?」
- 「内定承諾書にサインしたら、もう他の企業は受けられない?」
これらの疑問に答えるためには、「内定」と「労働契約」の法的関係を正しく理解することが重要です。本記事では、労働法の観点から、内定の法的性質について詳しく解説していきます。
1. 労働契約とは何か―基本から理解しよう
労働契約の定義と成立要件
まず、「労働契約」とは何かを確認しましょう。労働契約法第6条は次のように定めています。
労働契約法第6条 「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」
つまり、労働契約とは、「あなたが会社で働き、会社がその対価として給料を支払う」という約束のことです。民法上の契約の一種であり、双方の合意によって成立します(民法第522条第1項)。
契約成立のプロセス
一般的な契約は、以下のプロセスで成立します:
- 契約締結の誘引 – 企業が「うちで働きませんか?」と募集をかける
- 申込み – あなたが「働きたいです」と応募する
- 承諾 – 企業が「採用します」と回答する
民法第522条第1項によれば、承諾の意思表示がなされた時点で契約は成立します。では、就職活動における「内定」は、このプロセスのどこに位置づけられるのでしょうか?
2. 就職活動の流れと労働契約―どの段階で契約は成立するか
新卒採用の一般的なプロセス
新卒採用は、以下のような長期にわたるプロセスを経て行われます:
3年生の3月〜4年生の6月頃:就職活動期間
- 企業説明会への参加
- エントリーシート提出
- 筆記試験・面接試験
6月〜9月頃:内々定期間
- 選考通過の連絡(内々定)
- 内定承諾書の提出依頼
10月1日:正式内定
- 内定通知書の交付
- 内定式の開催
10月〜翌年3月:内定期間
- 内定者研修・懇親会
- 卒業見込み証明書の提出
- 健康診断
4月1日:入社
- 入社式
- 新入社員研修開始
各段階の法的性質
それでは、このプロセスの各段階は、法的にどのような意味を持つのでしょうか。
- 企業の募集活動 → 「契約締結の誘引」
企業が行う募集活動は、労働契約締結に向けた「誘引」にすぎません。つまり、「うちの会社に応募してください」という呼びかけです。 - 学生の応募・受験 → 「申込み」
学生がエントリーシートを提出し、採用試験を受けることが、労働契約の「申込み」にあたります。「私を採用してください」という意思表示です。 - 内定通知 → 「承諾」
企業が内定通知を出すことが、労働契約の「承諾」にあたります。これにより、原則として労働契約が成立すると考えられています。
3. 内定の法的性質―最高裁判例が示した重要な考え方
大日本印刷事件最高裁判決の意義
内定の法的性質について、最も重要な判例が「大日本印刷事件」最高裁判決(最高裁昭和54年7月20日第二小法廷判決・民集33巻5号582頁)です。
事案の概要: 大学4年生のAさんは、大日本印刷から採用内定通知を受け、誓約書を提出しました。ところが、入社2か月前になって、会社から「グルーミー(陰気)な印象なので不適格」という理由で内定を取り消されました。Aさんは、内定取消は不当だとして裁判を起こしました。
最高裁の判断: 最高裁は、以下のような画期的な判断を示しました。
「企業の募集に対する大学卒業予定者の応募は労働契約の申込であり、これに対する企業の採用内定通知は右申込に対する承諾であって、誓約書の提出とあいまって、これにより、大学卒業予定者と企業との間に、就労の始期を大学卒業の直後とし、それまでの間誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものと認めるのが相当である。」
「解約権留保付始期付労働契約」とは
最高裁判決が示した「解約権留保付始期付労働契約」という概念を、分かりやすく説明しましょう。
- 始期付(しきつき)労働契約
「始期付」とは、「いつから働き始めるか」という開始時期が決まっている契約のことです。内定の場合、通常は「翌年4月1日から」働き始めることが決まっています。 - 解約権留保付
「解約権留保」とは、一定の条件が発生した場合に、企業が契約を解除できる権利を持っているということです。ただし、この権利は無制限ではありません。
内定取消が認められる場合
最高裁は、内定取消(解約権の行使)が認められるのは、以下のような場合に限られるとしています:
「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる」
具体的には、以下のような場合が該当します:
正当な内定取消事由の例:
- 卒業できなかった場合(留年・退学)
- 必要な資格を取得できなかった場合
- 健康状態の著しい悪化により就労が困難な場合
- 重大な経歴詐称が判明した場合
- 犯罪行為を行った場合
不当な内定取消事由の例:
- 「印象が暗い」などの主観的理由
- 軽微なSNS投稿の内容
- 他社への就職活動継続(内々定段階)
- 会社の業績悪化(整理解雇の4要件を満たす必要あり)
4. 内定と内々定の違い―法的保護の程度が異なる
内々定の法的性質
「内々定」は、正式な内定通知(10月1日)より前に、企業が学生に対して「採用予定である」ことを伝える事実上の行為です。法的には以下のような違いがあります:
| 項目 | 内々定 | 内定 |
|---|---|---|
| 時期 | 6月〜9月頃 | 10月1日以降 |
| 法的性質 | 労働契約は未成立(通説) | 労働契約成立 |
| 取消の自由度 | 比較的広い | 厳格に制限 |
| 損害賠償責任 | 信義則違反の場合あり | 不当な取消は違法 |
内々定取消に関する裁判例
コーセーアールイー事件(福岡高裁平成23年3月10日判決・労判1020号82頁)では、内々定の段階でも、企業が学生に対して「ほぼ確実に採用する」という期待を与えた場合、その取消には信義則上の責任が生じうるとされました。
5. 実務的なアドバイス―就活生が注意すべきポイント
内定承諾書の法的効力
多くの企業は、内定通知とともに「内定承諾書」や「誓約書」の提出を求めます。これらの書類には、通常以下のような内容が含まれています:
- 入社の意思確認
- 他社の内定辞退の約束
- 内定取消事由の列挙
- 入社日の確認
重要なポイント: 内定承諾書に法的拘束力はありますが、憲法22条1項が保障する「職業選択の自由」により、入社前であれば内定辞退は可能です。ただし、民法627条1項により、2週間前までに申し出る必要があります。
内定期間中の過ごし方
やるべきこと:
- 卒業に必要な単位の確実な取得
- 必要な資格試験の準備
- 健康管理の徹底
- 内定先企業の研究・準備
避けるべきこと:
- SNSでの不適切な投稿
- 違法行為・反社会的行為
- 虚偽の報告(成績、健康状態など)
- 無断での長期海外渡航
内定取消を受けた場合の対処法
万が一、不当な内定取消を受けた場合は、以下の対応を検討しましょう:
- 取消理由の明確化を求める
- 書面での理由開示を要求
- 就業規則や内定通知書の確認
- 証拠の保全
- 内定通知書、メール、録音等の保管
- やり取りの経緯を時系列で整理
- 相談窓口の活用
- 大学のキャリアセンター
- 労働基準監督署
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー
- 弁護士(労働問題専門)
- 法的措置の検討
- 地位確認請求(従業員としての地位確認)
- 損害賠償請求(慰謝料、逸失利益等)
6. 関連する労働法規と今後の展望
関係法令一覧
- 労働契約法(平成19年法律第128号)
- 第6条(労働契約の成立)
- 第16条(解雇権濫用の禁止)
- 民法(明治29年法律第89号)
- 第521条以下(契約の成立)
- 第627条(雇用契約の解約)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)
- 第20条(解雇予告)
- 第22条(退職時の証明)
採用活動の適正化に向けた動き
厚生労働省は「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)に基づき、「事業主等指針」を定めています。この指針では、内定取消の防止や、やむを得ず内定取消を行う場合の配慮事項が示されています。
また、日本経済団体連合会(経団連)の「採用選考に関する指針」に代わり、政府主導の「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」が新たなルールを定めており、採用活動の適正化が図られています。
まとめ―内定は「スタート地点」
内定通知を受け取った時点で、法的には「解約権留保付始期付労働契約」が成立しています。これは、あなたと企業との間に既に法的な関係が生まれているということです。
しかし、内定はゴールではなく、社会人としてのスタート地点です。内定期間を有意義に過ごし、4月からの新生活に向けてしっかりと準備を進めましょう。同時に、自分の権利を正しく理解し、不当な扱いを受けた場合には適切に対処できる知識を身につけておくことも大切です。
最後に、就職活動は人生の重要な転換点ですが、一つの通過点でもあります。内定の有無にかかわらず、自分のキャリアを長期的な視点で考え、継続的な成長を心がけることが、充実した職業人生につながるでしょう。
次回は、内定期間中の注意点について考えてみます。
参考文献・判例
- 最高裁昭和54年7月20日第二小法廷判決(大日本印刷事件)民集33巻5号582頁
- 福岡高裁平成23年3月10日判決(コーセーアールイー事件)労判1020号82頁
- 菅野和夫『労働法〔第12版〕』(弘文堂、2019年)
- 荒木尚志『労働法〔第5版〕』(有斐閣、2022年)
- 厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」
Author Profile

-
特定行政書士
早稲田大学政治経済学部卒。立教大学大学院法務研究科修了、法務博士(専門職)。帝京大学や神田外語大学他首都圏の大学で企業研究・就職活動講義へ出講経験あり。就活塾の講師としても活躍。ブラック企業や就活塾に詳しい行政書士として朝日新聞・読売新聞の取材やNHK番組出演などの実績もあり。
Latest entries
 就活と法2025年11月11日内定もらうと労働契約スタート?就活生が知っておくべき基本知識を解説します
就活と法2025年11月11日内定もらうと労働契約スタート?就活生が知っておくべき基本知識を解説します 就活と法2025年11月10日こんな就活塾はヤバイ【悪徳詐欺就活塾の巧妙な手口と被害の実態 】
就活と法2025年11月10日こんな就活塾はヤバイ【悪徳詐欺就活塾の巧妙な手口と被害の実態 】 就活と法2015年10月24日入社するには身元保証が必要?
就活と法2015年10月24日入社するには身元保証が必要? 就活と法2015年8月24日試用期間の過ごし方
就活と法2015年8月24日試用期間の過ごし方